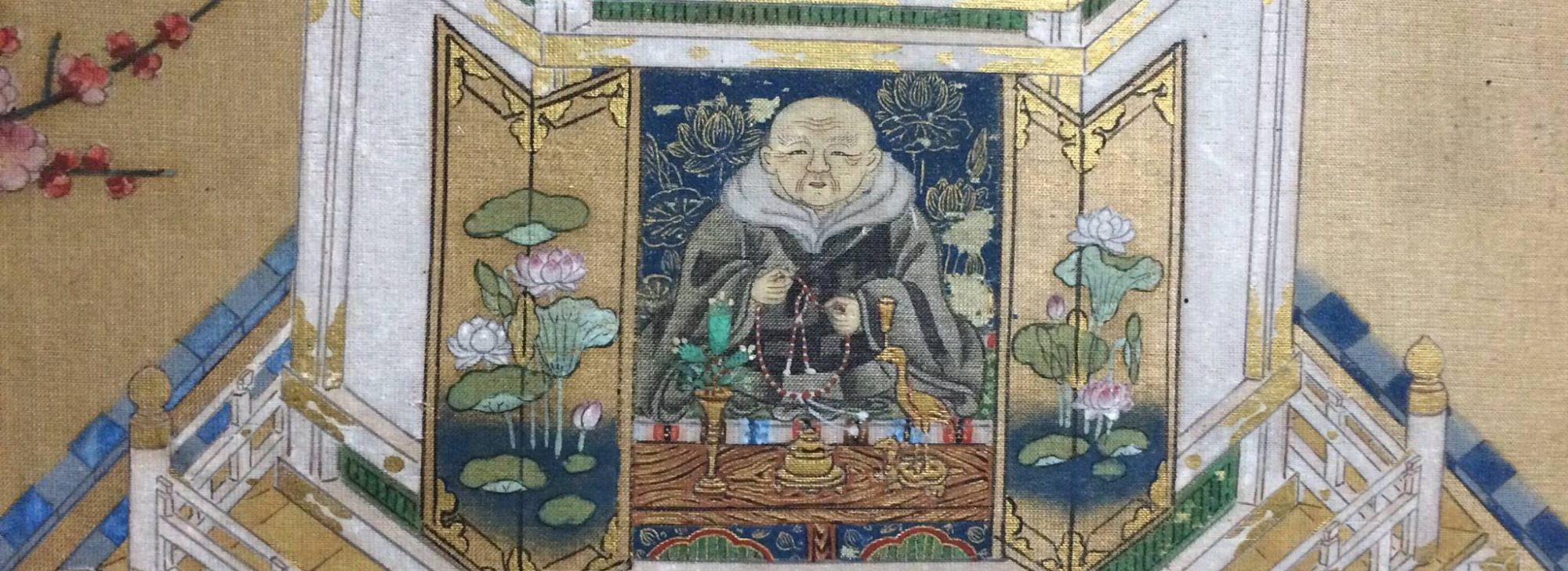≪市民放射能測定所設置(食品の測定)へ向けての準備をしています≫
御同朋の皆様
現在、福島県二本松市を初めとする中通り地域では、福島第一原発事故による放射能汚染によって、高い線量率の中、強制避難地域から避難してきた人も含めて100万人以上の人々が、今なお避難することもできず生活されています。
今、妊婦さんたち、子どもたちが汚染されていない地域へ避難できるよう手助けする運動が大切であると同時に、決して忘れてはいけないのは、避難できない妊婦さん、子どもたちがおられることです。妊婦さんたち、子どもたちのために少しでも被ばく量を減らす運動が、今、求められています。
そのための手立てとして、
①高線量率の場所を避けるためのガイガーカウンターを送る
②除染作業の方法論の構築及び、除染作業の道具を送る
③市民放射能測定室の設置。食品の放射能汚染度を測定し、妊婦さんや子どもたちが汚染された食品を口にしないような環境づくり。の三つが考えられます。
この中で、
①は、3万円~5万円あればガイガーカウンターが一台送れます。個人一人でもできます。
②は、道具を送ることはできますが、除染方法を確立するためには、専門家の手助けを得ながら、実地の実験を繰り返してデータを集め検討していく必要があります。ですので、線量率が高い地域でなければできません。
③は、放射能汚染によって、さらには食品の放射能測定を実施してくれない苦境の中で苦しんでいる人たちの手助けを確実に、そして世界のどこからでも参加できる運動です。そして、一人の力では、とても及ばない高価な機械が必要になるという点で、多くの人たちの協力が必要になります。
現在、福島県内では、福島市、郡山市、いわき市で市民放射能測定所を設置する動きが出はじめていますが、今回、真宗大谷派のご縁でつながりのある二本松市の市民と連携しながら、二本松市に市民放射能測定所を設置・運営していくための資金を広く募りたいと考えました。
その準備段階として、たんぽぽ舎をはじめとして、チェルノブイリ原発事故以降、東京都江東区、千代田区、小金井市、静岡県静岡市などで市民測定室にて食品の放射能測定に取り組んでこられた方がたに測定器の選定などについて助言をいただきながら、さらに専門家によるサポート、市民による運営体制の可能性を模索します。
募金は、まだ先になりますが、なにとぞご理解の上、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。
呼びかけ人を募集しています。お名前(○○県・職業など)を添えて、メールでご連絡ください。よろしくお願いします。メール:shiminsokuteijo●nanaoarchive.com
福島の子どもたちのために市民放射能測定所をつくる会
事務局:石川県七尾市相生町91番地 真宗大谷派常福寺内 畠山 浄
お問合せ メール:shiminsokuteijo●nanaoarchive.com 電話:0767-53-1392
除染作業の様子:『放射能汚染の現実を超えて共に生きたい』福島県二本松市 除染作業
http://johukuji.nanaoarchive.com/top/?p=1320